「女性が育児や家事をするのは当たり前」や「男の浮気よりも女性の浮気の方が悪い」
など古い考えなのは分かっているが、心のどこかで共感している自分がいました。
また日本では男は働き、女性は家の事をやるべきという考え方が根付いたのは、最近であるという話を聞き、この考えはなぜ起こるのかを考えてみた。
結論から言うと、儒教が大きく関係していることが分かった。
歴史を簡単にまとめると以下の通りである
①縄文〜弥生
→卑弥呼など、女性が強い社会。
②奈良〜平安
→儒教が導入される
③鎌倉〜室町
→武家社会により女性は家内に従属
④江戸
→儒教的教えが制度化
→家父長制…父が家族を支配(忠の実践)
→女大学という女子の教訓書が普及
⑤明治〜戦前
→儒教が軍国主義に悪用。
男は国のために死ぬ(忠の実践)
女は出産、育児、内助の功(三従の実践)
⑥戦後〜現代
→憲法による平等化
儒教の教え まとめ
- 仁 思いやり・人を大切にする
- 礼 礼儀・敬意・秩序を守る
- 義 正義・正しい判断
- 智 知恵・学び
- 信 信頼・誠実さ
● 孝(こう)=親孝行
→親や先祖を敬い、恩を大切にすること
● 忠(ちゅう)=忠義・誠実
→上の者に誠実に仕えること
● 生活の中の意識[社会秩序の柱]
→上のものは下の者を率い
→父は子を率い
→夫は妻を率いる
●「女子三従(じょしさんじゅう)」:女性は一生誰かに従う存在とされる
- 少にしては父に従い(少女時代は父に従い)
- 嫁しては夫に従い(結婚後は夫に従い)
- 老いては子に従う(夫の死後は息子に従う)
→ 女性は常に他者(主に男性)の庇護のもとで生きるべきとされ、自立や主体性を否定される考え。
● 貞節・従順・家のために生きる美徳
- •女性は「貞淑(ていしゅく)」であることが求められ、不倫や再婚は非難された
- •夫が亡くなっても再婚しない「貞女」は理想の女性像とされ、美談として語られた
- •教育も「良妻賢母」になるための道徳・礼儀が中心(知識や職能ではない)”
まとめ
縄文時代以前は卑弥呼が国家の最高責任者になるなど、平等及び女性が優位であった。奈良平安時代に儒教が日本に伝わり、江戸時代では儒教を国家の理念として制度化。農工商にも広く道徳として認知された。
戦前には軍国主義を正当化する為に儒教を悪用され「親に逆らわない」「国のために尽くす」ことが美徳とされ、戦争協力の正当化に利用されたということだった。
儒教は宗教というよりは道徳に近いものだが、調べるとまさに父、祖父世代のステレオタイプの日本人そのものだった。
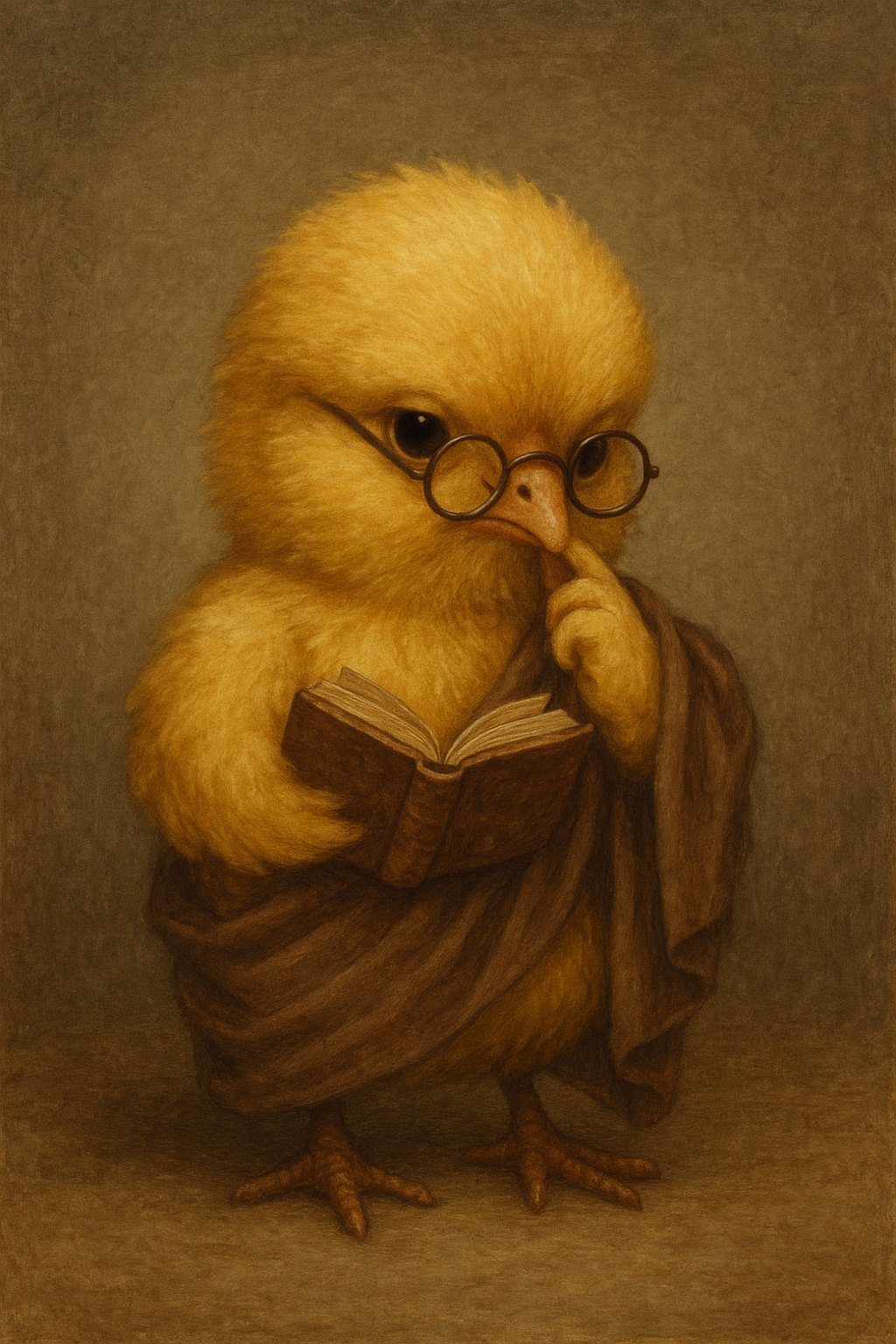
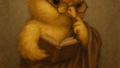
コメント